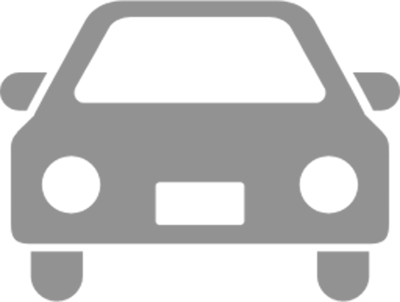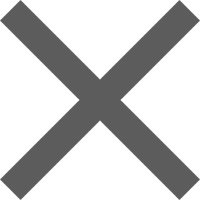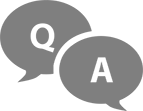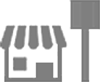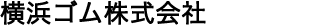偏摩耗防止のために
偏摩耗とは「靴のかた減り」のような現象で、タイヤに対してさまざまな力=ストレスが働くことにより発生します。
偏摩耗が
発生すると
- タイヤの寿命が縮む。
- 操縦安定性が低下する
- 燃費が悪化する。
タイヤ経費削減のためには
偏摩耗防止が欠かせません。
主な発生原因
- 空気圧の不適正。
- アライメントの不適正。
- ローテーション不足。
- 車両整備不足。
- 複輪外径差、空気圧差。
特に空気圧管理とローテーション
実施が偏摩耗予防に有効です。
代表的な偏摩耗
センター摩耗
タイヤの中央部(センター)が早く摩耗したもの。
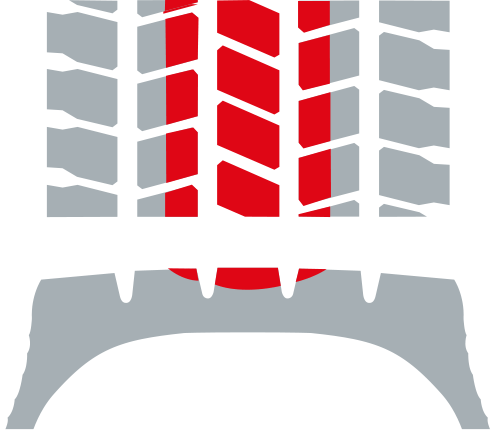
発生原因
- 空気圧が高すぎる。
- 駆動力の高い車両の駆動軸で使用した時に起こりやすい。
多角形摩耗
真横から見て多角形型に摩耗したもの。
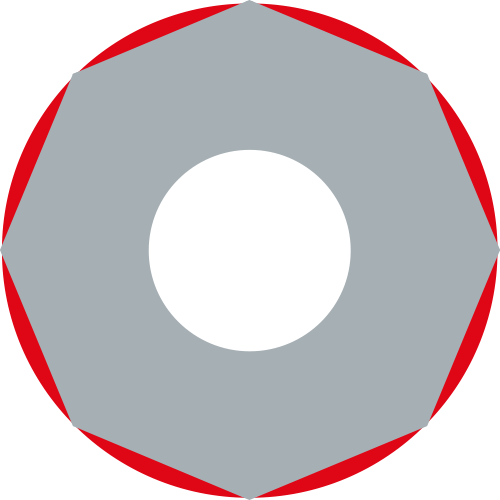
発生原因
- ベアリングとキングビンのガタ。
- ハブおよびスピンドルの偏心、曲がり。
- 回転部分のアンバランス。
- アライメント(トー、キャンバー)の不適正。
スポット摩耗
タイヤの1ヵ所のみ局部的に摩耗が進んだもの。
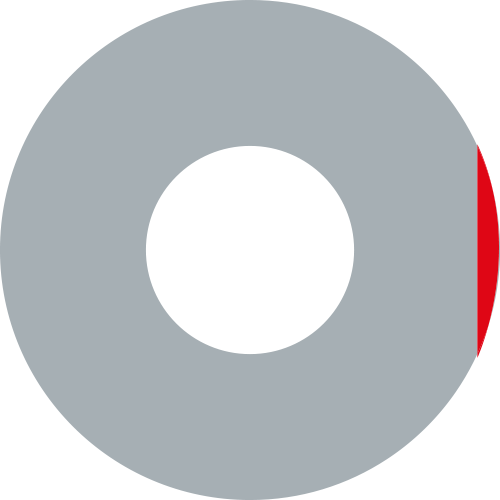
発生原因
- 急ブレーキ、急発進。
- ブレーキドラムの偏心。
- 回転部分のアンバランス。
肩落ち摩耗
トレッド全体に比べショルダー部のみが溝を境に“段”がついたように早期に摩耗したもの。
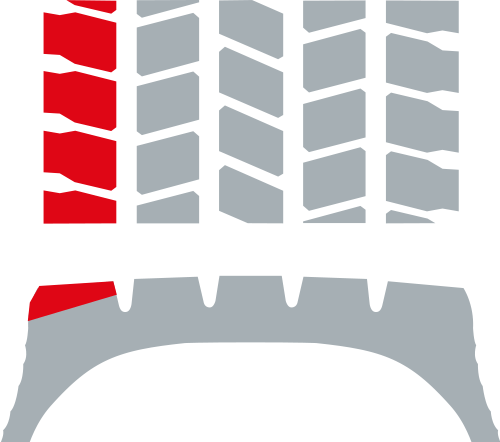
発生原因
- フロント装着時のトーイン、キャンバーの影響。
- 急カーブの走行が多い。
- 路面傾斜の影響で発生する場合がある。
ステップ摩耗
ショルダー部の外側が集中的にすり減ったもの。
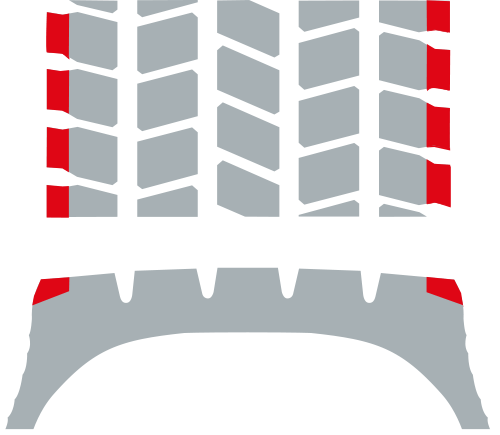
発生原因
- フロント装着時のトーイン、キャンバーの影響。
- 急カーブの走行が多い。
- 路面傾斜の影響で発生する場合がある。
波状摩耗
トレッドショルダー部に多く見られ、波状に摩耗したもの。
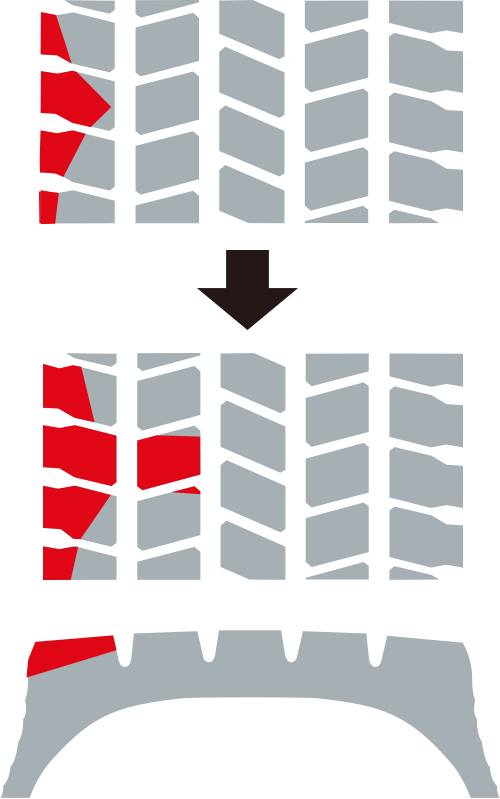
発生原因
- トーイン、キャンバーの不適正。
- 空気圧不足。
- 複輪外径差、空気圧差。
ヒール&トウ摩耗
ブロックがのこぎり刃状に摩耗したもの。

発生原因
- 制動・駆動の頻度が高い。
- 空気圧不足。
両肩落ち摩耗
タイヤの両ショルダー部が早期に摩耗したもの。
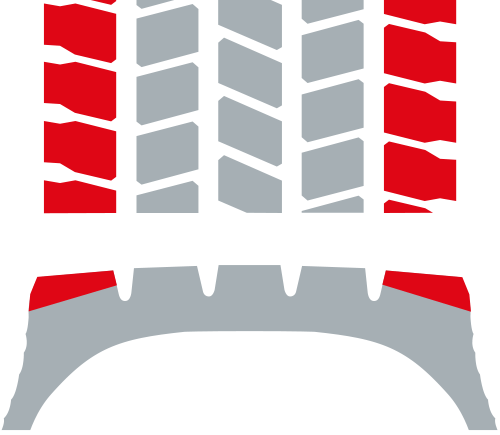
発生原因
- 空気圧不足。
- 過荷重。
レール摩耗
タイヤの溝の縁部が、レールが通ったようにすり減ったもの。
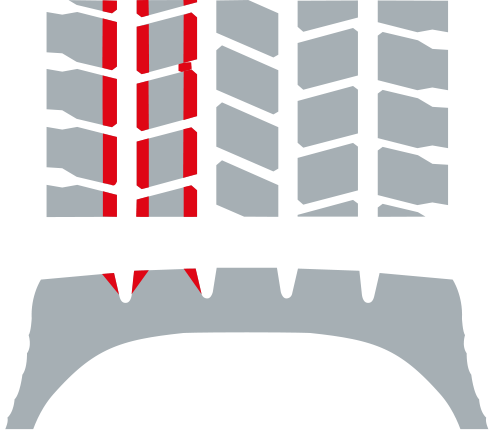
発生原因
- アライメントの調整不足。
- ローテーション不足。
リブパンチング
ショルダー部を除くある一定の列のブロックのみが早期に摩耗したもの。
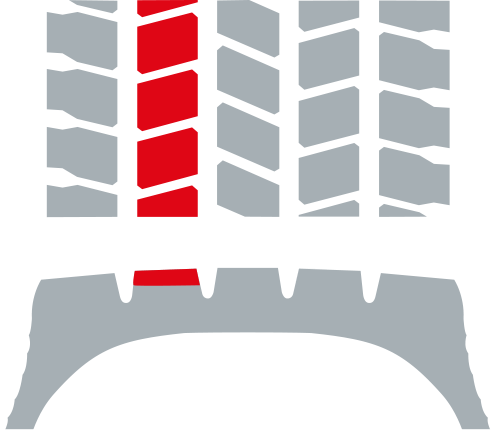
発生原因
- 複輪外径差、空気圧差。
- フロント使用でもアライメントの影響で発生することがある。
フェザーエッジ摩耗
リブおよびサイプエッジに多く見られ、タイヤの断面方向にのこぎり刃状に摩耗したもの。
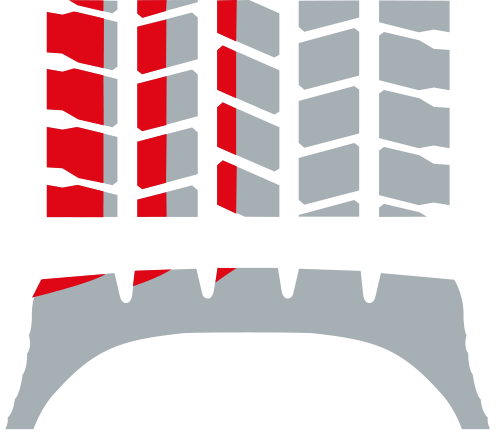
発生原因
- 主にトーイン不良。
- 空気圧不足。
- 急カーブの走行が多い。
- 路面傾斜の影響で発生する場合がある。
片側摩耗
トレッドの片側のみ早期に摩耗したもの。
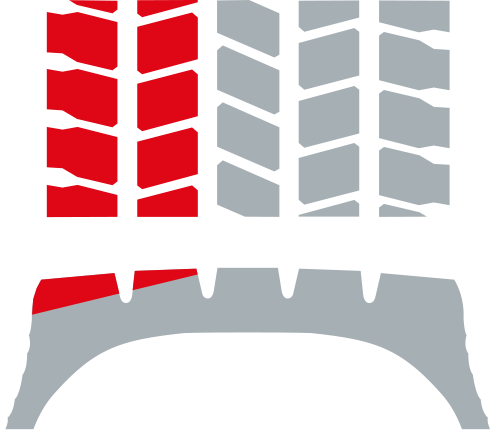
発生原因
- 主にフロント装着時のキャンバーの影響。
- 急カーブの走行が多い。
- 路面傾斜の影響で発生する場合がある。
タイヤのメンテナンスについて
偏摩耗にはこまめにタイヤローテーションを!
効果的なローテーション
- 「ヒール&トウ摩耗」の成長途中で行う
ヒール&トウ摩耗が成長しきってしまうと、いくら逆回転に装着しても直すのが難しくなるので、1回目のローテーションは早めに行うことが望ま しいです。目安として3,000~5,000kmをお薦めします。
- 進行の早いタイヤに合わせて行う
通常フロントタイヤのヒール&トウ摩耗の成長が早いので初回の交換は、フロントタイヤに合わせて行うのが効果的です。
ここがポイント
- 1回目のローテーションは早めに行う。
- 回転方向を逆にする。
- 偏摩耗が成長する前に、ローテーションを行う。
- 駆動輪・遊動輪間のローテーションを行う。
トラック・バス用タイヤの位置交換例
2-B
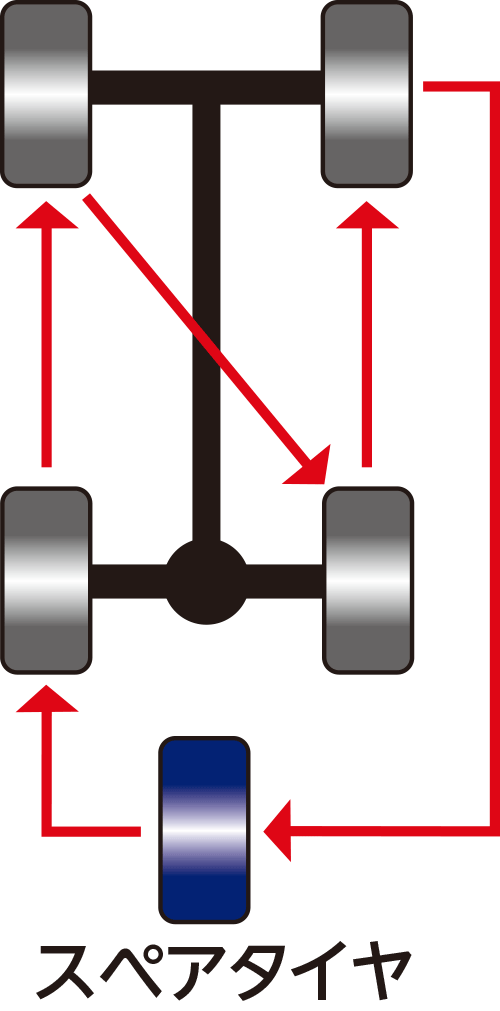
2-D
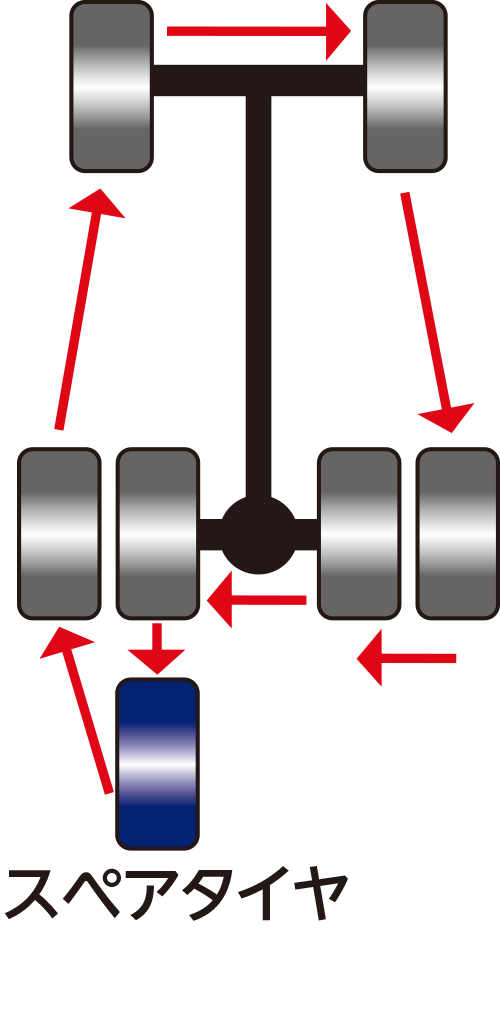
2-D(巡回型)
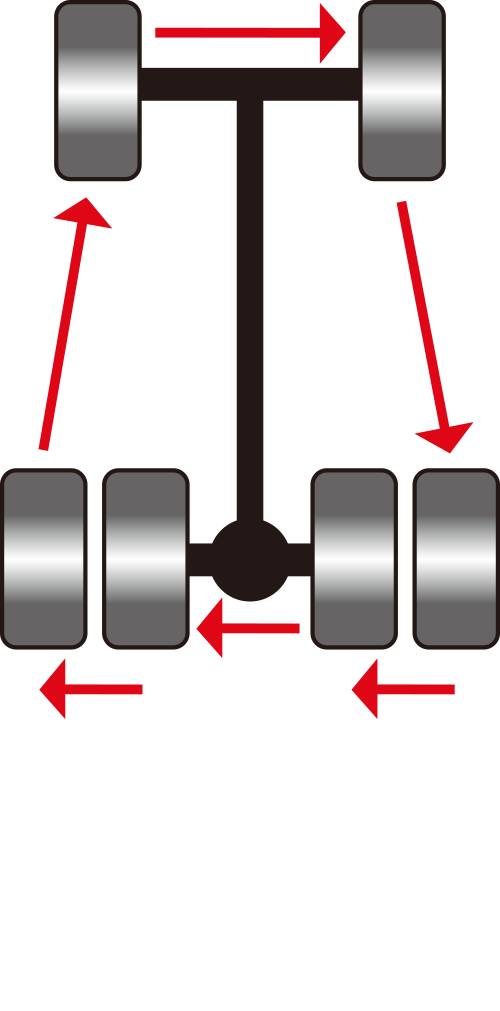
2-D(前後型)
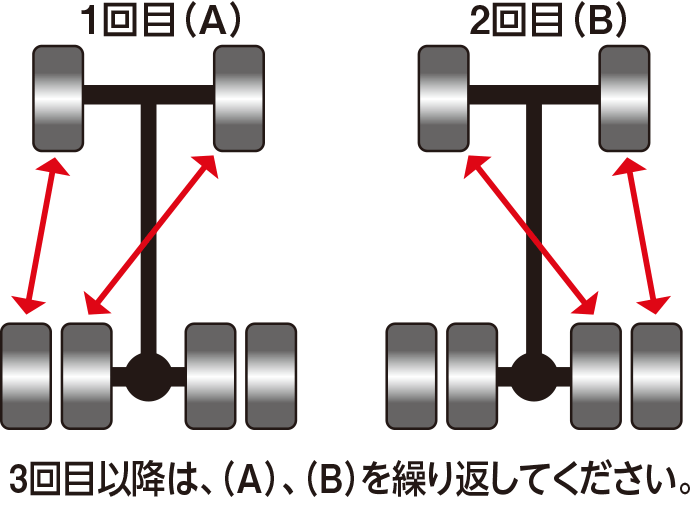
前後異サイズの場合は、同サイズでローテーションを行う。
2・2-D(前後型)
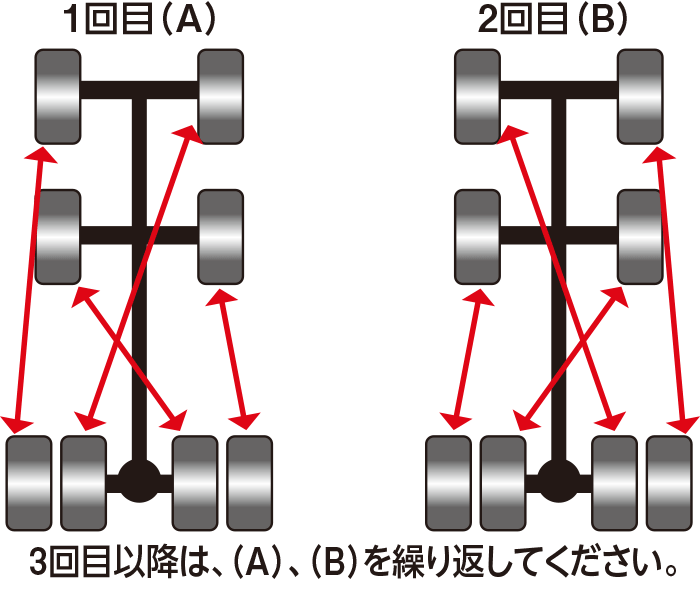
2-D・4、2-D・D(前後型)
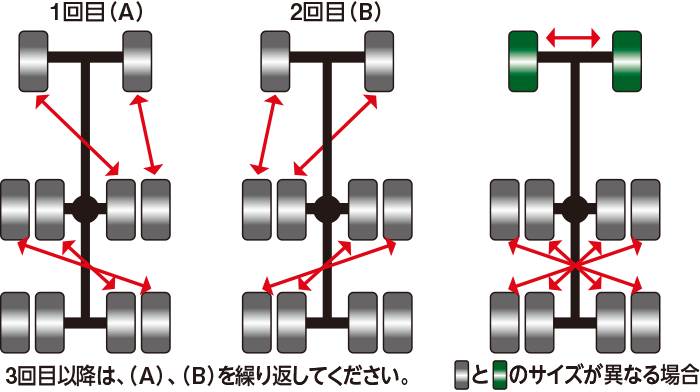
2・2-D(巡回型)
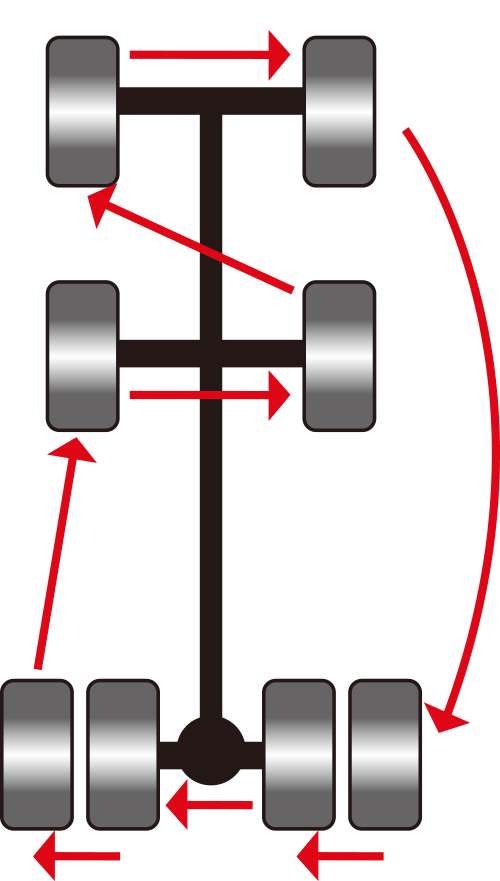
2・2-D・D
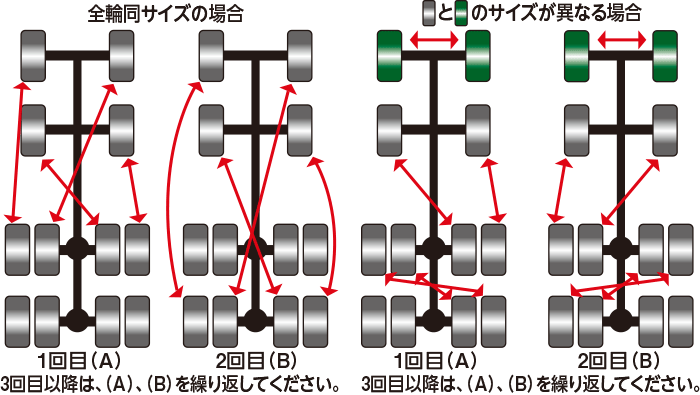

 乗用車用タイヤ検索
乗用車用タイヤ検索