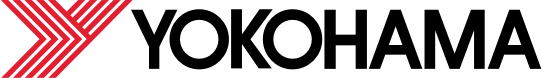労働慣行
多様性と機会均等
KPI
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 項目 | 2021年度実績 | 2022年度実績 |
|---|---|---|
| 女性の従業員比率 | (連結)12.0% (国内)7.5% |
(連結)14.0% (国内)7.2% |
責任部門
人事部
考え方・目標
なぜ「人材の多様性」が重要取り組み項目なのか
理由と背景の解説
2021年度よりスタートした新中期経営計画「YX2023」では深化×探索による変革を掲げています。その目標達成のためには、多様な人材が多様な働き方を認め合い、これまでのルールや考え方にとらわれない働き方や、共に明るく生き生きと仕事ができる職場環境を整えるなど、人材の多様性をさらに推進していくことが重要な課題と認識しています。
目指す姿(達成像)/目標
国籍、性別やLGBTQ+といった属性や学歴、経験にとらわれない採用を行い、YX2023の事業戦略、技術戦略の実現に向けて最適な人材の配置がなされている状態を継続していきます。
また、ワークライフバランスを尊重し、多様な人材、多様な働き方を認め合うことで、すべての社員が成長を続け、キャリアを形成できる職場を目指します。
また、ワークライフバランスを尊重し、多様な人材、多様な働き方を認め合うことで、すべての社員が成長を続け、キャリアを形成できる職場を目指します。
目指す姿に向けた施策
目指す姿を実現するため、次の施策を展開しています。
<多方面からの人材登用>
新卒者は長期的視野に立って安定的に採用しています。また事業のニーズに応じて経験のある方の採用(キャリア採用)をしています。
また、シニア層人材、社内早期登用など様々な方面から仕事に応じた最適な人材を登用・配置していきます。
また、シニア層人材、社内早期登用など様々な方面から仕事に応じた最適な人材を登用・配置していきます。
<障がい者の雇用>
障がい者雇用につきましては、これまで、既存業務内でハンディキャップにかかわらず活躍できる仕事を中心に、各事業所で定期的な新卒受け入れをしてきました。今後も、障がい者雇用の幅を広げるにあたり、新たな業務の開発を進めています。
<各種制度による多様な働き方の支援>
在宅勤務制度の拡充、コアタイムを撤廃したフレックスタイム制度、短時間勤務制度など、場所・時間を問わない勤務制度の拡充を通じて、ワークライフバランスを改善することで、いつでもどこでも仕事でしっかり成果が出せる仕組みを整えています。また、育児休業制度、介護休業制度、配偶者同行休業制度、キャリアリターン制度などを拡充することで、介護や育児などの人生イベントがあっても継続したキャリア形成が可能な仕組みを目指しています。
<セミナーなどによる支援>
ダイバーシティ推進の一環として、仕事と生活の両立支援制度の整備を行うとともに、無意識の偏見の排除、イクボス推進教育、LGBTQ教育など多様性を認める風土を推進する啓発活動を実施し、働きやすい環境を整えています。また、ダイバーシティ・マネジメント力の強化セミナー、女性活躍推進を目的としたキャリア開発支援セミナー、育児両立社員の交流会、健康セミナー(メンタルヘルス対策、ハラスメント防止施策、乳がん、子宮がん等)など、多様な人材の活躍支援を目的としたセミナーを各種開催しています。
2022年度の活動レビュー
2022年度、人材の多様性の確保と、均等な機会の提供について、次の活動を行い、成果をあげました。
多様な総合職の採用
2014年7月の地域限定総合職制度導入から、継続して各拠点で実施・展開をし、現在まで4拠点で地域限定総合職採用につながっています。
<安定的な新卒採用と事業戦略に応じたキャリア採用>
2022年度の新卒採用は31名となりました。
総合職の採用は中途採用も含めて合計62名で、女性の比率は16.1%です。
総合職の採用は中途採用も含めて合計62名で、女性の比率は16.1%です。
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
女性採用数(総合職:新卒+中途)(単位:名)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
|---|---|---|---|
| 女性 | 17 | 9 | 10 |
| 男性 | 51 | 13 | 52 |
| 計 | 68 | 22 | 62 |
| (女性比率) | 25% | 41% | 16% |
(中途採用者には正社員登用者も含む)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
年齢別、男女別、駐在国別従業員数(単独)(単位:名)
| 社員区分 | 性別 | 日本 | アジア | 北米 | 欧州 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 社員 | 女性 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 男性 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | ||
| 契約社員 | 女性 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 30-50歳 | 社員 | 女性 | 233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 男性 | 3,119 | 37 | 16 | 4 | 0 | 3,176 | ||
| 準社員 | 女性 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 契約 | 女性 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 男性 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| 50歳超 | 社員 | 女性 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 男性 | 1,189 | 42 | 10 | 1 | 4 | 1,246 | ||
| 準社員 | 女性 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 契約 | 女性 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 男性 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||
| 70歳超 | 契約 | 男性 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 5,516 | 91 | 27 | 5 | 5 | 5,644 | ||
<特例子会社 ヨコハマピアサポート(株)での障がい者の雇用>
ヨコハマピアサポート(株)は、横浜ゴムの特例子会社として、障がい者の雇用の場を創出する目的で2012年に設立しました。
障がい者雇用数は、業務の拡大により雇用の場を創出しながら、設立時から毎年、定期的な実習生の受け入れ、採用を継続しています。
2023年4月現在、知的障がい者を中心に48名(うち知的障がい者31名)が在籍しています。
業務は、平塚製造所の中で、160カ所を超えるトイレや各種会議室、休憩室などの清掃をはじめ、緑化作業、郵便や社内メールの仕分け・配送、名刺の作成などを行っています。
仕事は個人の特性に合わせて配置をした上で、業務の範囲が増えたり、新人指導ができるようになる等、スキルアップすることで少しずつ評価が上がる制度も見直し、人材育成に力を入れています。
当社のOBを中心とした指導員が日々、丁寧に指導を行うことで、障がいのある従業員一人一人が安心して業務に取り組める職場環境づくりを心掛けています。
日々の相談だけではなく、半年に1回、個別面談を実施することで、キャリア、要望、悩みなどを把握し、定着率の向上にも努めています。
今後も、安全・基本をしっかり守りながら、プロ集団になるべく業務遂行をし、長く活躍できる職場づくりを目指していきます。
また、横浜ゴム、ヨコハマピアサポート、ヨコハマタイヤジャパン、横浜ゴムMBジャパンの4社で障がい者雇用率制度および障がい者雇用納付金制度上の関係会社特例認定を受け、4社合算しての雇用率は、2022年申告(2021年4月~2022年3月実績)で2.67%となりました。
障がい者雇用数は、業務の拡大により雇用の場を創出しながら、設立時から毎年、定期的な実習生の受け入れ、採用を継続しています。
2023年4月現在、知的障がい者を中心に48名(うち知的障がい者31名)が在籍しています。
業務は、平塚製造所の中で、160カ所を超えるトイレや各種会議室、休憩室などの清掃をはじめ、緑化作業、郵便や社内メールの仕分け・配送、名刺の作成などを行っています。
仕事は個人の特性に合わせて配置をした上で、業務の範囲が増えたり、新人指導ができるようになる等、スキルアップすることで少しずつ評価が上がる制度も見直し、人材育成に力を入れています。
当社のOBを中心とした指導員が日々、丁寧に指導を行うことで、障がいのある従業員一人一人が安心して業務に取り組める職場環境づくりを心掛けています。
日々の相談だけではなく、半年に1回、個別面談を実施することで、キャリア、要望、悩みなどを把握し、定着率の向上にも努めています。
今後も、安全・基本をしっかり守りながら、プロ集団になるべく業務遂行をし、長く活躍できる職場づくりを目指していきます。
また、横浜ゴム、ヨコハマピアサポート、ヨコハマタイヤジャパン、横浜ゴムMBジャパンの4社で障がい者雇用率制度および障がい者雇用納付金制度上の関係会社特例認定を受け、4社合算しての雇用率は、2022年申告(2021年4月~2022年3月実績)で2.67%となりました。
制度による支援
<育児休業制度>
法定の育児休業(育児休業A)に加え、多様な育児サポートのニーズに合わせて1日単位で10日間育児休業を取得できる制度(育児休業B)や、休業中に就労できる産後パパ育休制度(育児休業C)を導入し、男性社員も育児参加しやすいようにしています。その結果、2022年の男性育休取得率は59.5%※でしたが、100%を目標に育休取得を推奨しています(女性の育休取得率は100%)。
- 2022年に出生があった男性社員のうち、同年中に育児休業A、B、Cのいずれかを1日以上取得した人数の割合
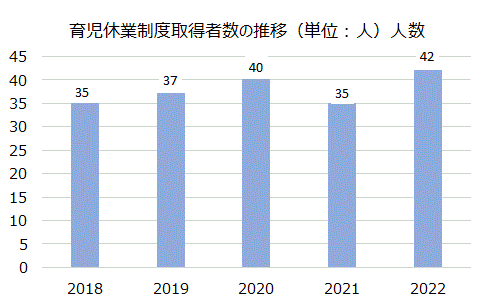
育児休業制度(育児休業A)取得者数の推移(単位:人)人数
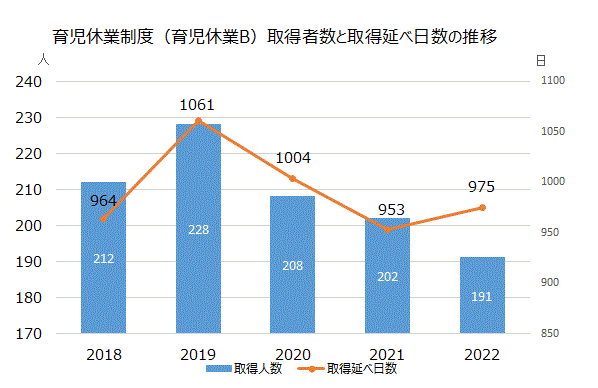
育児休業制度(育児休業B)取得者数と取得延べ日数の推移
<介護休暇・休業制度>
介護休暇は有給で取得可能とし、毎年多くの社員が利用しています(法定では無給)。
また、積立年休を年5日まで介護のために利用することも可能です。
介護休業制度は通算で最長1年、10分割まで(法定は最長3カ月、3分割まで)取得可能とし、長引く介護生活と両立できるように配慮しています。
また、積立年休を年5日まで介護のために利用することも可能です。
介護休業制度は通算で最長1年、10分割まで(法定は最長3カ月、3分割まで)取得可能とし、長引く介護生活と両立できるように配慮しています。
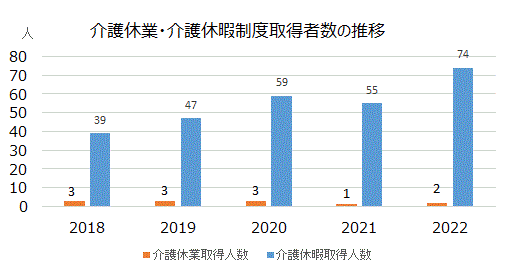
介護休業・介護休暇制度取得者数の推移(単位:人)人数
<短時間勤務制度>
小学校6年生までの子(法定は3歳未満の子)をもつ社員、または介護を必要とする親族をもつ社員は、本人の希望により短時間勤務制度が適用されます。2023年からは短時間勤務フレックスタイム制度を設け、仕事と家庭の両立がより柔軟にできるようになりました。
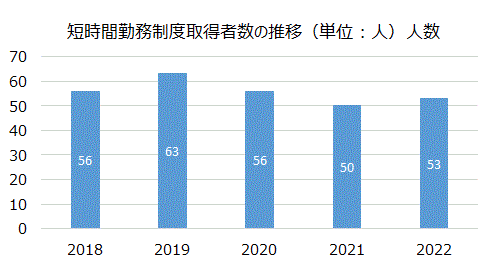
短時間勤務制度取得者数の推移(単位:人)人数
<育児介護相談窓口の設置>
2019年より各事業所に育児介護相談窓口を設置し、従業員の育児介護に関する悩みや困りごとに早期に対応できる体制を整えています。2022年の相談件数は全社で62件でした。
<在宅勤務制度/フレックスタイム制度>
仕事と育児・介護などの家庭の両立支援の推進および業務効率化の向上・長時間拘束防止(健康配慮)・通勤負担軽減を目的として2018年より在宅勤務制度、フレックスタイム制度を導入しています。
2020年にはコアタイム無しのフレックスタイム制度を導入、2023年には本社・平塚製造所の統合を機に、在宅勤務の週の利用上限を制度上撤廃し、長距離通勤者などへ対象者を拡大することで、さらなる働き方の多様化を図っています。
2020年にはコアタイム無しのフレックスタイム制度を導入、2023年には本社・平塚製造所の統合を機に、在宅勤務の週の利用上限を制度上撤廃し、長距離通勤者などへ対象者を拡大することで、さらなる働き方の多様化を図っています。
ホームオフィス制度
本社・平塚製造所の統合後の遠距離通勤者を対象に、オフィスに固定デスクを持たず、会社負担で自宅をオフィス化し、基本的な就業場所とする「ホームオフィス制度」を導入しました。また、ホームオフィス制度利用者とのコミュニケーション促進を目的に、フリーアドレス形式で、カフェスペースを備えたサテライトオフィスを開設しました。なお、配偶者の転勤に同行する社員もホームオフィス制度を利用できるよう整備し、家庭の事情でキャリアが中断することのないよう配慮しています。
地域限定社員制度
小学校入学までの子どもを持つ者、要介護の家族を持つ者に対し、希望に応じ2年間転勤を停止する地域限定社員の制度を導入しています。
配偶者の転勤同行に伴う休業制度
配偶者の海外・国内転勤同行に伴う休業制度を導入しており、これまで8名の社員が利用しています。
キャリアリターン制度
配偶者の転勤同行、育児介護を事由とした退職者を対象としたキャリアリターン制度を導入しており、これまで1名の社員が制度を利用して再入社をしています。
有給休暇の時間単位取得制度
2018年より仕事と家庭の両立支援の推進を目的として、有給休暇の時間単位取得制度を導入しました。
2022年は1,215名の社員が利用しました。
2022年は1,215名の社員が利用しました。
事例紹介
山東横浜ゴム工業制品有限公司(YRSC)での男女平等等の推進
YRSCでの女性の就業率は従業員数全体の10.0%、女性管理職4名配置、管理職全体の21.1%となります。
昇格昇進に男女の格差はありません。新規採用においても、個人の希望と能力を尊重しての配属を行っています。また社内の社宅施設の有効活用として、一室を託児所として活用し、働き盛りのご夫婦への育児支援も行っています。
昇格昇進に男女の格差はありません。新規採用においても、個人の希望と能力を尊重しての配属を行っています。また社内の社宅施設の有効活用として、一室を託児所として活用し、働き盛りのご夫婦への育児支援も行っています。


ダイバーシティ&インクルージョン推進タスクの活動
横浜ゴムでは2016年に、女性活躍推進法に対応するため、「女性活躍推進タスク」を立ち上げ、「多様な働き方を認め合い、長く働きやすい会社を目指す」という方針のもと、各種施策の実施と諸制度の拡充を進めてきました。
2018年には在宅勤務制度、短時間勤務期間の延長、時間単位有給休暇の取得等、働きやすい制度の導入・拡充を図りました。
それと並行して、全社員への介護アンケート、ヒアリングの実施、および女性復職者への総合的な支援施策として、ワーキングマザー交流会や40歳以上の女性のためのエンカレッジセミナー、育休者向けキャリアセミナー、健康セミナーなどを実施しました。
2019年には、さらなる施策として、妊娠〜復職までのフォロー体制の構築、復職部下上司向け・本人向けセミナー、介護セミナー、役員向け働き方改革講演会などを実施しました。 また、タスクの名称を「ダイバーシティ推進タスク」へ変更し、女性に限定せず、多様なメンバー(若者、シニア、女性、LGBTQ+、障がい者など)による生産性向上と新しい価値を生み出すために、さらに幅を広げて活動の推進を図りました。
2020年には、「多様な働き方」をテーマにWEBセミナーに切り替えて開催するとともに、在宅勤務アンケートや管理職ヒアリングなどを実施しました。
2021年には、「ダイバーシティの深化」をテーマにwwP(work with Pride)※に参加し、ダイバーシティ調査などを実施しました。
2022年はダイバーシティマネジメントセミナー・女性向けリーダーシップセミナーなどを実施しました。職場のLGBTQ+に関する意識調査も実施しました。
2023年からはタスクの名称を「ダイバーシティ&インクルージョン推進タスク」へ変更し、より多様な人材を受け入れてさらにお互いを尊重しあえる職場環境づくりを推進します。
2018年には在宅勤務制度、短時間勤務期間の延長、時間単位有給休暇の取得等、働きやすい制度の導入・拡充を図りました。
それと並行して、全社員への介護アンケート、ヒアリングの実施、および女性復職者への総合的な支援施策として、ワーキングマザー交流会や40歳以上の女性のためのエンカレッジセミナー、育休者向けキャリアセミナー、健康セミナーなどを実施しました。
2019年には、さらなる施策として、妊娠〜復職までのフォロー体制の構築、復職部下上司向け・本人向けセミナー、介護セミナー、役員向け働き方改革講演会などを実施しました。 また、タスクの名称を「ダイバーシティ推進タスク」へ変更し、女性に限定せず、多様なメンバー(若者、シニア、女性、LGBTQ+、障がい者など)による生産性向上と新しい価値を生み出すために、さらに幅を広げて活動の推進を図りました。
2020年には、「多様な働き方」をテーマにWEBセミナーに切り替えて開催するとともに、在宅勤務アンケートや管理職ヒアリングなどを実施しました。
2021年には、「ダイバーシティの深化」をテーマにwwP(work with Pride)※に参加し、ダイバーシティ調査などを実施しました。
2022年はダイバーシティマネジメントセミナー・女性向けリーダーシップセミナーなどを実施しました。職場のLGBTQ+に関する意識調査も実施しました。
2023年からはタスクの名称を「ダイバーシティ&インクルージョン推進タスク」へ変更し、より多様な人材を受け入れてさらにお互いを尊重しあえる職場環境づくりを推進します。
- work with Pride:企業のLGBTQ+に関するダイバーシティ・マネジメントの定着と促進を支援する団体。
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
ダイバーシティ関連の主な教育プログラム
| 年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プログラム数 | 16 | 8 | 17 | 15 | |
| 延べ参加人数※ | 503 | 214 | 327 | 181 | |
| 主なプログラム | ダイバーシティ | ・ダイバーシティプログラム ・多様な人材のマネジメント |
・多様な人材のマネジメント強化 | ・多様な人材のマネジメント強化 ・wwP※への参加 |
・ダイバーシティ教育 ・ダイバーシティ、マネジメント強化 ・wwP※への参加 |
| 女性のキャリア開発 | ・エンカレッジ ・キャリアアップ ・スキルアップ |
・エンカレッジ ・ビジネススキルアップ |
・エンカレッジ ・ビジネススキルアップ |
・女性向けリーダーシップセミナー | |
| 両立支援 | ・復職者キャリア ・復職者上司 ・プレママ交流会 |
・復職者キャリア ・ワーキングマザーファーザー交流会 |
・復職者キャリア ・ワーキングマザーファーザー個別相談会 |
・復職者キャリアセミナー ・ワーキングマザーファーザー個別相談会 | |
| 健康介護 | ・乳がん/睡眠対応 ・介護離職防止 |
・COVID-19予防対策 | ・介護離職防止/介護とお金の話 | ・産後ケア教室支援 |
- 延べ参加人数:全社員教育を除く
- wwP:work with Pride
多様な社員一人一人が尊重され、活躍できる組織風土づくりのためには、管理職の意識がポイントとなります。
そこで、管理職向けダイバーシティ推進プログラムとして、体系的にダイバーシティ・マネジメント研修を実施する一方、多様な社員の活躍支援として、女性のキャリア形成支援、仕事と育児・介護との両立支援、障がい者・LGBTQ+の活躍支援等を引き続き実施していきます。
多様な人が多様な働き方をすることを認め合えるような風土を醸成し、すべての社員にとって、働きがいのある、長く働き続けられる会社を目指していきます。
そこで、管理職向けダイバーシティ推進プログラムとして、体系的にダイバーシティ・マネジメント研修を実施する一方、多様な社員の活躍支援として、女性のキャリア形成支援、仕事と育児・介護との両立支援、障がい者・LGBTQ+の活躍支援等を引き続き実施していきます。
多様な人が多様な働き方をすることを認め合えるような風土を醸成し、すべての社員にとって、働きがいのある、長く働き続けられる会社を目指していきます。
今後の課題
これからはダイバーシティだけでなくインクルージョンの実現に向けた各種施策を講じていくことが課題です。多様性を受け入れるだけでなく、それぞれの個人が自身のアイデンティティを尊重され、全ての人が自然な形で組織に参加できる環境を作り出すことが求められます。
そのため制度の理解と浸透、制度の利用促進のため、教育や研修などを通じてインクルーシブな組織文化を築くための施策を積極的に講じていきます。
そのため制度の理解と浸透、制度の利用促進のため、教育や研修などを通じてインクルーシブな組織文化を築くための施策を積極的に講じていきます。