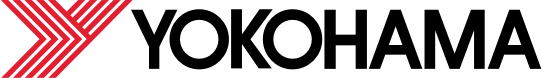横浜ゴムの重要課題(マテリアリティ)
重要課題(マテリアリティ)
横浜ゴムは、2014年に社内の議論およびステークホルダーの意見を踏まえて重要課題(マテリアリティ)を特定しました。マテリアリティは、環境変化等を受けて2017年、2020年に見直しを実施しています。現在、次期中期経営計画の策定および社会環境の変化に対するマテリアリティの見直しを進めています。
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 重要課題(マテリアリティ) | 認識する課題 | ||
|---|---|---|---|
製品を通して |
安心と楽しさをいつまでも届けます  |
| |
地球環境のために |
豊かな自然を次世代へ伝えます     |
| |
人とのつながり |
共に高め合い笑顔を広げます    |
| |
地域社会と共に |
共に生き、ゆるぎない信頼を築きます     |
| |
| コーポレート ガバナンス  |
グローバル化する社会的課題に正しく対処するための基盤を強化します   |
| |
重要課題(マテリアリティ)の特定
2013年5月、持続可能性報告書の国際的ガイドラインを策定・発行する国際NGOであるGlobal Reporting Initiative(GRI)は、内容をこれまでの「網羅的な情報開示」から、「重要課題(マテリアルな側面)に焦点を当てた情報開示」を求めるものへと改訂したGRIガイドライン第4版(G4)を発行しました。これは、経営がCSRにより深く関与することで、企業がより積極的な意思を持ち、CSRレポートで報告する内容を決定していくことを目的としたものです。横浜ゴムはG4準拠に向けて、2014年に以下の手順で重要課題(マテリアリティ)を特定しました。
STEP1 G4ギャップ分析
「CSR レポート2013」の情報開示レベルをG4の要請に照らし、対応項目と未対応項目の内容と程度について現状を把握しました。
(2014年1月実施)
(2014年1月実施)
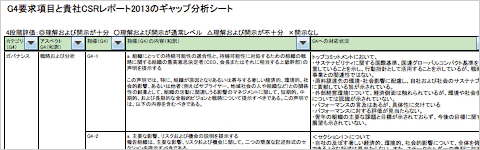
STEP2 社内で課題の優先順位を整理
当社の業種、事業分野、事業地域に即して分析を実施。その後、関連部署との協議により当社における課題の優先順位を整理しました。
(2014年1~2月実施)
(2014年1~2月実施)
評価の事例
「サプライヤーの環境評価」:原材料として天然ゴムを調達する横浜ゴムにとって、自社の範囲を超えたサプライチェーンの上流での森林破壊や違法伐採などの環境リスクや強制労働や児童労働などの潜在的な人権リスクへの配慮が重要な課題です。また、当該リスクは、先進国から開発途上国に至る国・地域での当社グループの広範な事業展開を考えると、非常に顕在化しやすいものと考えられます。この点を社内の担当者と協議する中で、「重要度が高い課題」と評価しました。
STEP3 課題の優先順位に外部視点を反映
ステークホルダー5人へのインタビューを実施。インタビュー結果を踏まえ、外部視点を反映した課題の優先順位を決定しました。
(2014年2~3月実施、肩書きは実施当時)
(2014年2~3月実施、肩書きは実施当時)

河口 真理子氏
株式会社大和総研 調査本部 主席研究員
企業の社会的責任(CSR)、社会的責任投資(SRI)の観点から、持続可能な社会実現に向けた提言を数多くの企業に行っている。
企業の社会的責任(CSR)、社会的責任投資(SRI)の観点から、持続可能な社会実現に向けた提言を数多くの企業に行っている。
人権、多様性、男女同一報酬、苦情処理制度、顧客の個人情報保護といった重要な課題とともに、注目したいのが「腐敗防止」です。多くの国では、腐敗防止に関する専門の省庁や委員会があり、行政が組織横断的に汚職を管理します。日本で考える以上に腐敗防止に対する意識は高いです。国連グローバル・コンパクトでも独立した原則として明記されています。
グローバル化が進んだ現在、非常に重要な問題として、腐敗防止に関する明確な方針と対応策を講じておく必要があると思います。
グローバル化が進んだ現在、非常に重要な問題として、腐敗防止に関する明確な方針と対応策を講じておく必要があると思います。

熊谷 謙一氏
日本ILO協議会 編集企画委員
ISO26000の国際起草委員会委員をはじめ各種CSRについての国内外の審議に参加している。日本労働法学会の会員。
ISO26000の国際起草委員会委員をはじめ各種CSRについての国内外の審議に参加している。日本労働法学会の会員。
「労働安全衛生」や「労使関係」の側面について、社会全体がどのようなことに関心を持っているかを把握し、情報開示をしていく必要があります。たとえば、メンタルヘルスへの取り組みは、どの企業でも非常に関心の高い事項ですし、これまでも労使協議をきちんと続けてきたことを開示することで、海外進出時などには労働者の権利を尊重していることを正しく伝えることができます。また、今後グローバル展開を活発化するにあたっては、女性役員の積極的な登用が必須となってくるでしょう。

黒田 かをり氏
一般財団法人CSOネットワーク事務局長・理事
コミュニティの発展と参画を専門とし、福島の農業者等と「地域の力」フォーラムを立ち上げ、アジア地域との交流も実施する。
コミュニティの発展と参画を専門とし、福島の農業者等と「地域の力」フォーラムを立ち上げ、アジア地域との交流も実施する。
現在、企業は自社だけでなくバリューチェーンにおける社会的責任が求められています。たとえば、ゴム農園などの原材料生産地域では、どのようなリスクが発生しやすいかについて現状把握をする必要がありますし、自社においてもバリューチェーンにおいても、人権に関する苦情処理制度をきちんと整備して、対応していることを発信することが非常に重要だと思います。特に人権への取り組みについては、国内のみで事業を行っているときとは違う目配りがグローバル展開では必要になってきます。

関 正雄氏
明治大学経営学部特任准教授
株式会社損害保険ジャパン CSR 部上席顧問
ISO26000策定時に、日本の産業界代表として参画。さまざまな国際会議で持続可能な発展における議論に参加している。
株式会社損害保険ジャパン CSR 部上席顧問
ISO26000策定時に、日本の産業界代表として参画。さまざまな国際会議で持続可能な発展における議論に参加している。
事業をさまざまな地域で展開していく際に重要な観点は、地域での雇用にどれだけ貢献するかという点です。雇用への貢献は国内外での大きな関心事であり、企業として強く意識すべき点だと思います。また、持続可能な社会を目指す際に忘れてはならないのが、消費者に対しての、持続可能な消費についての教育啓発です。たとえば、「生態系への配慮」という観点を製品に組み込んで消費者へ訴求するなど、横浜ゴムのブランド価値向上につなげるコミュニケーションにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

竹ケ原 啓介氏
株式会社日本政策投資銀行 環境・CSR 部長
フランクフルトに計6年駐在し、「DBJ環境格付融資」を開発するなど日本の環境金融の第一人者として知られる。
フランクフルトに計6年駐在し、「DBJ環境格付融資」を開発するなど日本の環境金融の第一人者として知られる。
重要課題の選定にあたっては、地域特性以外に、時間軸を考慮する必要があると考えます。たとえば、現段階でビジネスを行っている地域のリスクはきちんと把握しているし、コントロールもできているかもしれませんが、今後、中長期的に新興市場のウェイトが高まると、現在はコントロールできているはずのリスクがもっと大きなものになることがあります。その意味で「現状の課題とマネジメント報告」、「中長期のビジョンと課題認識」の両方をうまくメッセージとして発信していただきたいと思います。
STEP4 重要課題の特定
ステップ2、ステップ3の重要度分析・調査・協議結果を踏まえて、2014年に以下の重要課題を選定しました。
- []カッコ内はGRI Standardにおいて名称が変更となった、マテリアリティに対応するGRI Standardの項目です。
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 地球環境 | 青い地球と人を守るために、環境との調和を通じた持続可能な社会づくりに挑戦します |
|
|---|---|---|
| お客さま | 心と技術を込めたモノづくりにより安全・安心な商品を提供します |
|
| 地域社会 | 地域社会の繁栄・発展に貢献し、社会からゆるぎない信頼を得ている地球貢献企業になります |
|
| 従業員 | 人を大切にし、人を磨き、人が活躍する場をつくります |
|
| 株主・投資家 | 事業を成長させ企業価値を高めます |
|
| 取引先 | バリューチェーンを通じたCSR活動を推進します |
|

株式会社クレアン 主任研究員 内田 宏樹氏
G4への対応の準備として、これまでSTEP1~STEP4の支援をいたしました。今後は、自ら設定したKPIに沿う形で、マネジメントを進めていくこととなりますが、ここで満足してしまうことなく、PDCAの実践を通じての確実なスパイラルアップや、メリハリをつけたCSRの取り組みを進めていかれることに期待します。その際、マテリアリティに選ばれた領域は全社的なマネジメントを通じて「横浜ゴムならでは」という取り組み事例を作り出し、情報開示を通じて発信していただきたいと思います。またマテリアリティに選ばれなかった領域でも、これまでの取り組みを継続しながら適宜情報開示を行うことで、全体として、活動の着実な底上げを目指していただきたいと思います。